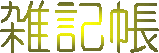 |
☆別のページが開きます |
top
|
"Black Rose"の原曲探しのことを書いたので、ついでに帰国後に入手したCDについて。
"The Long Black Veil" The Chieftains
バレン・ツアーのバスで流されていて、ミック・ジャガーの声に気付き、運転手さんに教えてもらった(第9日)。チーフタンズなら日本でも入手可能と考えて現地では買わなかった。日本では輸入盤はなかったので、結局割高になっちゃったけど、これは大当たりの1枚。
曲はほとんどがトラッドで、しかも有名なものが多いが、それを豪華ゲストが演奏してるのがミソ。
ミック・ジャガー、マリアンヌ・フェイスフルがヴォーカルで、マーク・ノップラーはギターとヴォーカルで参加してる。ベテラン勢はいずれも味わい深くて素晴らしい。この人たちは「渋」「枯れ」系だけど、スティングはサッカーの応援歌にしたらかっこよさそうな高揚感のある曲を歌ってる。
シンニード・オコナーもヴォーカルで参加。2曲あるが、どちらも有名な曲だ。
自分の一番のお気に入りゲスト、ライ・クーダーが2曲。ギターなどで参加のインストゥルメンタル曲と、ギターと歌で参加した曲があるが、どちらもライ・クーダー節を満喫できる。他にもシンニード・オコナーが歌っている2曲にギターなどで参加し、曲に陰影を与える演奏をしている。
その他ストーンズ、ヴァン・モリソン、トム・ジョーンズが参加してる。
コスト・パフォーマンス高い!
"Riverdance"
Sligoのツーリスト・オフィスで流されていた(第16日)。それ以前にもケリーかディングルのツアー・バスで聴いたように思う。
アイリッシュ・ダンスを中心としたダンス・ショーの音楽。このショーは日本でも何回か公演があって人気を博したので、日本でも入手できた。
ただ音楽としてはアイリッシュ・トラッドだけではないし、ダンス用のアレンジなので、思ったほどハマれなかった。
"At Their Best" The Dubliners
"Black Rose"に使われている"The Mason's Apron"の音源として買った。このバンドは長く活躍しており、アルバムは彼らの'60年代から'70年代初めのライブを集めたもの。27トラックも入ってるが安かったという記憶がある(千数百円)。新宿のHMVだったかな。
アイルランドのパブでのトラッド演奏をそのまま聴いてる感じの臨場感が良い。しかも有名なトラッドばかり。"Foggy Dew"、"The Rocky Road To Dublin"、"Wild Rover"、"Roisin Dubh"など。輸入盤で解説がないので、どの曲がどのくらい有名なのかわかんないけど。
弦楽器演奏の"Roisin Dubh"が美しい。
Sligoのツーリスト・オフィスで見つけたCongのイラスト・マップに、"Harry Clarke Stained Glass"の文字を見たときの印象は、「マジ、あのハリー・クラーク?」
自分の知ってるハリー・クラークのイメージは、教会のステンド・グラスとはあんまり結びつきそうもないものだったからだ。しかし、そこに載ってるステンド・グラスの写真、聖女らしい人物像にはまさしくハリー・クラークの絵柄の特徴があった。
へええ、ステンド・グラスのデザインもやってたんだ。たしかに絵描きがステンド・グラスのデザインを手がけるのは珍しくない。ラファエル前派のバーン・ジョーンズもやってるし。ふーん、ハリー・クラークがねえ。
ハリー・クラークのイラストを初めて見たのは高一のとき。だから、やっぱりかなり古い「知り合い」と言える。
創元推理文庫から出ていた「ポオ小説全集」全4巻(ポオてエドガー・アラン・ポーのことね)を入手したのだが、各巻の口絵がハリー・クラークのものだった。
他にも各巻の解説部分に何点か彼のイラストが載っていたが、とにかく強烈な印象で、一度見たら忘れないって類のものだった。
まず思ったのは、ビアズリー・フォロワーっぽい、ってことだ。
ビアズリー(*)といえば、モノクロのペン画でアール・ヌーボーに特徴的なうねる曲線を自由に操った装飾と、空白と黒ベタを効果的に配置した大胆な構図だ。エロティックで美しいがグロテスクでもある。
ハリー・クラークのポー・シリーズもモノクロのペン画で、装飾性に満ち、細かい描き込みのややグロテスクな雰囲気や人物の配置などにビアズリー的要素が見られる、が。
装飾的描き込みの細かさが半端じゃない。わずかな余白を残してほぼ全画面が埋め尽くされてたりする。偏執的というか、その細かさ自体に不気味さを感じるというか。
人物もたいていが指の先まで尖ったような細身で、神経質そうな顔に描かれている。
正直言って美しい絵柄じゃない。けどインパクトは強い。
ビアズリーもポーの作品を題材にしたイラストを描いている。得意の曲線と余白と黒ベタを駆使して不安げな雰囲気を醸している。しかし。
ポー的な雰囲気というならクラークのシリーズの方がフィットしてる。
かなり神経質でアル中気味で、精神的に不安定だったらしいポーは、病的な幻想性に満ちた作品をいくつか書いている。その息の詰まるような感覚には、クラークの病的なほどの細部の描き込みと神経質っぽい人物像がまさにぴったりなのだ。
*ビアズリーは19世紀末に活躍した、アール・ヌーボーを代表するイラストレーター。オスカー・ワイルドの戯曲「サロメ」に付けたイラスト・シリーズが出世作にして代表作。
今にして思えば、クラークの空間を埋め尽くす傾向は、あるいはケルト的なものの表出なのかも知れない。Book of Kellsに代表されるケルティック・デザインは、しばしば空間恐怖的に画面を装飾で埋め尽くす。
はい、知りませんでした、ハリー・クラークがアイルランド人だったとは。今回の旅行で彼のステンド・グラスの存在を知るまでは。
だってインパクトは強烈だったけど好きになったわけじゃなかったので、彼のことも他の作品のことも調べなかったからね。
さて例のCongのイラスト・マップを見せたところ、友人Mも美術畑なのでハリー・クラークのことは知っていた。で、自分が帰国した後、Mからさらに情報がもたらされた。
Mが訪れたアラン諸島のイニシュマン島にも、ハリー・クラークのステンド・グラスが入った教会がある、という。後日、Mが撮った写真も見せてもらった。
さすがに気になってインターネットで調べてみたら、ちゃんと見つかりました、経歴や作品例が出てるサイト(ここ)。
なんと、ハリー・クラークはステンド・グラス作家の息子で、若い頃からステンド・グラスのデザインを数多く手がけ、賞を獲ったりもしてたのだ。絵描きの余技なんかじゃなく、ステンド・グラス作家にして絵描き、だったらしい。
また彼のカラー作品も初めて見たが、色彩が美しく、デュラックやカイ・ニールセン(*)を思わせる作風のものもある。
へええ、そーだったんだー。
ただステンド・グラスでもカラー作品でも、やっぱり細身の人物が神経質っぽい顔してるけど。
「知り合って」からン十年後に知った真実、でした。
*Edmund DulacとKay Nielsen。どちらも19世紀末に生まれ、20世紀初頭に活躍した挿し絵画家。ハリー・クラークとほぼ同年代。
ポケットティッシュは日常の必需品、まして旅行中をおいてをや。
アイルランドのポケットティッシュは、パッケージが日本のよりやや細長い。その分、紙が細かくたたんであるのか、やや厚みがある。
ブランドもので見かけたのは、Kleenex。他にブランドじゃないのもあり、値段は少し安いが紙質も少し落ちる。ちょっとがさついてるというか。ま、それは日本でも同じ。
で、自分は手に入る限り、Kleenexを使っていた。
ところでこのKleenex、何故かパッケージには"Kleenex for men"とプリントされていた。柄はたしか黒と白のチェックかなんかで、雰囲気的には"for men"て感じではある。
そしてさらに、何故か1組が4枚重ねなのだ。日本のはふつう2枚重ね。
紙質がいいのに4枚いっぺんに使うのは勿体ないので、いちいち2枚ずつに分離して使っていた。たしか1パック10組入りだったと思うが、倍に使えてなんとなくお得な気がしないでもなかった。
しかし、なんで4枚重ねなんだろう? "for men"と関係があるのか? もしかして、男性特有の用途を意識してのことなのか?
そして旅行中ついに、"for men"じゃない、ただの"Kleenex"あるいは"Kleenex for women"というものには、お目にかかれなかったのである。
W杯サッカーが大詰めを迎えている。
アイルランドは惜しくもベスト16で終わったが、多くのサッカーファンと多くのにわかファンに強い印象を残した。
どこが相手でも手抜きなしの本気勝負。しかも1点先行されて最後にぎりぎり追いつくという劇的展開を2回もやったのだ。
決して諦めず、器用とは言えない戦術を執拗に繰り返し、ついに1点をもぎ取る。この過程で先行しているはずの相手は次第に追いつめられ、見ている我々はいつの間にかアイルランドの得点を期待している。
緊張感に満ちたゲームとサッカーの本質とも言える「1点のもたらす歓喜」を味わわせてくれたアイルランド・チームは、ちまたで人気急上昇である。
TV中継の解説者も言ってたが、アイルランドの選手たちは、失点しても好機を逸しても、PKを外してさえ気落ちしない。最後の1秒まで、ただ1つのゴールに挑戦し続ける。
このメンタリティはどこから来るのか。
不利な、あるいは勝ち目の薄い戦い(おもに対英独立の)を続けてきた歴史に培われたのか。
'95年の旅行のときだが、ふとアイルランドのサッカーはどうなってるのか、と思い、まず雑誌を探した。
世界のサッカーを扱った雑誌はすぐに2,3冊見つかった。しかし国内リーグの情報が出てない。やっと見つけた国内リーグの雑誌は表紙も編集もなんか地味だった。
スポーツ用品店にも行ってみた。レプリカ・ユニフォームのコーナーに、代表チームのものは見つかった。しかし他はイングランドのプレミア・リーグのばっかりだ。
パブのTVでサッカーの放送やってたが、よく見たらプレミア・リーグのチェルシーとどっかの試合だった。
たまたま会話する機会があった子供たちも、サッカーのことはリバプールがどうとか、って、やっぱりプレミア・リーグだった。
何しろ、アイルランドの代表チームはほとんどの選手がプレミア・リーグ所属だし。
どーもアイルランドの国内リーグは影が薄い。
その'95年の旅行の最後の日曜日、バスに乗って出かけて、スポーツイベントのサポーターたちにでくわした。
最初ダブリンの街角にちらほら見かけたのが、中心街からやや離れたところでどっと数が増えた。とある交差点近くの歩道で、ビールを飲んで気勢を上げるサポーターの大群が車道にまで溢れ出て、遙か彼方までの渋滞の原因になっていた。その源泉となってるらしい方向を見たら、大きなスタジアムがあった。
最初はサッカーのサポーターかと思った。でもよく見るといでたちが微妙に違う。チームカラーのハンチングみたいな帽子被ってる人が多かったり。
帰りに同じ経路をバスで戻ってきて、ちらっと見えたスタジアムは試合中らしく、スタンドがぎっしり埋まってた。
夕方、ダブリンの街に試合後のサポーターたちが繰り出してきたのにも遭った。勝った方はビールのグラスを持ったままバスに乗ってきてはしゃいでたり、車の窓からでっかいフラッグなびかせて走ってたり。
ホテルの部屋に帰ってから、何の試合だったのか知りたくてTVを見てた。どうやらゲーリック・フットボールだったようだ。やっぱサッカーじゃなかった。
サッカーの試合でもあんなふうに盛り上がってるんだろか(あの影の薄さが気になる)。
ところでアイルランドとイングランドの代表チームの対戦て、どんな感じなんだろう。
最近のW杯本戦ではもちろん対戦はなかったが、欧州地区予選とか欧州選手権で対戦したって話も、自分は寡聞にして聞いてないのだが。一度見てみたい、いや、現場観戦は遠慮だけど(^^;。
その1 おやつりんご
昨年暮れに知り合いからリンゴが1箱送られてきた。
嫌いじゃない。が、最近あんまり食べてなかった。
手に取って思う、いつから日本のリンゴはこんなにでかくなったのか。
要するに一度で1つ食べきれる大きさじゃないのが、食べなくなった主たる原因なのだ。
そりゃ、家族とかで分けて食べりゃいいわけである。じゃ、世の中にいっぱいいる一人暮らしの人は? 一人じゃなくても、食べたいときにいつもシェアする人がいるって、一般的な状況と言えるかな?
つまり必要以上に大きいリンゴは気軽に食べられない。すると消費が減る。安いリンゴを多く作っても売れないから、ますます大きく甘い品種で贈答用なんかの生産にシフトしていく。ま、想像なんだけど(でもそんなにかけ離れてない気がする)。
旅行中はリンゴよく食べた。だって食べやすいから。でかいスコーン食べた後でも1個食べられる適度な大きさ。それに手に入りやすい。なんせコンビニで山盛りにしてバラ売りしてるもん。もちろん甘くて美味かった。
日本の美味いリンゴのためにも、食生活の実態に合った生産と流通になって欲しいんだけどな。
その2 中身が選べるサンドイッチ
そういう店に行きたいとき、日本だとサブウェイくらいしか思い浮かばない。まあ探せばあるのかも知れない、デパ地下とか。でも簡単には見つからないように思う。
サブウェイだってチョイスにそんなにバリエーションないし、チェーンだからどこの店でも同じだし。なんか選ぶ楽しさ、あんまり感じない。
旅行中、弁当で一番多かったのはもちろんサンドイッチ。ま、サンドイッチ文化の国だから美味いです。で、中身もパンの種類も選べる店がすぐ目に付く。中身選ぶのはいつも楽しかった。好きなのはハム、トマト、チーズに、あればコールスローで、ありきたりなんだけど、すごくバリエーションが多い店もあった。ライスサラダなんかあったりして。
バリエーションと言えば、セルフサービス・カフェの食べ物も種類が多かった。セント・スティブンス・グリーン・ショッピング・センターのKylemore Cafeなんか、スコーンの類はもちろんカレーもあるし、ケーキやデザートも目移りするほど、リンゴやバナナもある。
そもそもセルフサービス・カフェそのものが多い。日本でもずいぶん普及してきたけど、ほとんどがチェーン店で、だからどの店でも置いてるものが同じ。スターバックスはチョイス多いみたいだけど、でもまだまだって感じだ。
もしかしたら、食品衛生法(だっけ?)なんかの規制でできないものがあるのかも知れない。
けど、国民性というか文化のせいかも、って気もする。
選ぶということには、自己責任が伴うわけだけど、日本人、これ、苦手っぽい。自分で選ぶより「おまかせ」「おすすめ」に頼ったり、自分でするよりサービスしてもらう方が得、って傾向ないかな。提供する側もあらかじめセットメニューかなんかにして、選ぶ面倒省くのがサービスと思ってたりね。
サンドイッチの中身くらい主体的に選んでも、大した自己責任なんかありゃしないって。
バレン・ツアーでちゃんと見せてもらえなくて未練を残したドルメン(旅日記「第9日」)。古代の巨石文化の産物とされ、でっかい石の柱を立てた上にでっかい屋根みたいな石を乗っけたものだ。上に乗ってる石は大きいものなら100トンにもなるという。巨石文化は世界のあちこちに見られるが、どうやって建造したのか、何のために、など、常に謎に満ちてる。(参考写真)
ところで、自分がこの「ドルメン」を知ったのはけっこう古い。アイルランドがらみのものでは一番古くから知ってるかも知れない。たぶん小学3,4年くらいだったと思う。
学校の図書室で借りた本の中に出てきたのだ。タイトルは「三十棺桶島」。
横溝正史もぶっとぶ強力インパクトだが(単純計算で「八ツ墓村」の3.75倍)、怪盗ルパン・シリーズの一つだった。もちろん、読んだのは子供向けのやつだが。
しかし実は、さすがにタイトルは忘れなかったものの、内容はほぼ完全に記憶から欠落しているのである。ルパン・シリーズであることは覚えているのに、ルパンがどうやって登場してどう活躍したか、まっっったく覚えていない。
わずかに覚えているのは冒頭のシーンだけ。
ルパンとは別に主人公にあたる女性がいて、たしか彼女が故郷の田舎町に帰ってきたところかなんかから始まる。そして町のあちこちで、自分では書いたはずがない、自分のサインを見つける。そのあたりの描写が実に無気味くさいつうか、いかにもこれから禍々しいことが起こりそうな気配が濃厚に漂う。そういう雰囲気だけ妙によく覚えている。
そのサインに導かれて、彼女は「三十棺桶島」に渡るのだが、そこで彼女を待っていたものは…
なんだったんだろう? じぇんじぇん覚えてない。
が、待ってはいなかったと思うが、ドルメンが「三十棺桶島」にはあった。
何故ドルメンだけ記憶に残ったのか?
思うにやっぱり、子供心にも巨石を積んだ古代の遺跡は謎めいて気になったんでしょーな。
それと、「ドルメン」って言葉の響きね。どこか神秘的つうか呪術的な古代っぽい雰囲気がある。「ストーン・ヘンジ」はまだしも(でも半端に即物的だ)、「ストーン・サークル」なんつう味も素っ気もない「まんま」な名称に比べて、言葉そのものが謎めいてる。なんせ、何語かよくわかんないし。
ただ、ルパン・シリーズだけに、ドルメンがある「三十棺桶島」はアイルランドではなかった。フランスのどっかだったな、という記憶はあったが、最近調べてみたら、舞台はブルターニュだった。
ブルターニュにはアイルランドと共通するケルト文化が残ってるそうだ。ドルメンはケルトより遙か昔のものなので、この場合関係ないのだが。
にしてもドルメンて何語なんだろう?
アイルランドに出逢ったのは、フクシアの項でもマイケル・コリンズの項でも書いた小説"The Wrath of God"である。中学生のときのことだ。
これはあくまでも文字情報で、ヴィジュアルとしてのアイルランドに出逢ったのは、高校生になってからだ。
昼休みにはよく図書室に入り浸っていたが、ある日、普段は手に取ったことがないアサヒグラフを開いた。いつ発行されたものだったかまでは覚えていない。
そして覚えているのは2葉の写真。
1つはベトナム戦争の写真で、米軍兵士が死体を手で「ぶら下げて」いる、キョーレツ極まる映像だ。片手で持ち上げられるほどに破壊された人間の身体(つーか、ボロです、はっきり言って)、しかも子供のように見える。
戦争の残虐性をストレートに、これ以上ないほど具体的に見せつけられたこの写真は、石川文洋氏(*)が撮ったものだと後に知った。
もう1つ。酸鼻の極みの戦場写真と同じ号に載っていたと思うが、古い記憶なので他の号だったかも知れない。
画面のほとんどが木々の緑、それも雨上がりらしく、しっとりつややかで、その緑に染まるように円環が付いた不思議な形の石の十字架が立つ。
見るだけで画面の中の清涼な空気が感じられるような写真。キャプションなんか忘れたが、それがアイルランドの風景であることだけは記憶に残った。
写真誌なんだから、他にも写真がたくさん載っていたはずだ。石川氏の戦場写真の方は、誰が見ても一生忘れそうもないくらいインパクトがある。
が、アイルランドの緑の墓場にも、他の幾多の写真を押しのけて長く残るほどの強い印象があったわけだ。
今にして思えば、この緑と円環十字架の写真は、アイルランドの視覚的イメージを表すティピカルな風景なのだった。
緑はナショナルカラーかつアイルランドの枕詞、円環十字架はケルト文化の象徴、どちらもアイルランドの「ウリ」である。とは言え、他の国の観光資源(たとえばフランスでもイタリアでもスペインでも)に比べてなんとも地味な「ウリ」である。
しかし、だ。この二つが組み合わさった風景は、アイルランドについてほとんど知らないガキの記憶に、有無を言わさず焼き付いたのである。
やはり「ウリ」になるべきほどのものだったのだ。
にしても墓場の風景がその国の魅力を語るということもあるんですな。日本の墓場の風景は、日本の観光の宣伝に使えそうもないけど。
もっとも円環十字架(ケルト十字架)は、もともと死者のメモリアルだったわけではないらしい。古い時代(9,10世紀頃)の大きなもの(ハイクロスという)は、キリスト教の説教用だったという説も聞く。だから自分が昔見た写真も墓場ではなかった可能性もある。
だが、現在見られる円環十字架のほとんどは、墓地に墓石として立っている。
中にはかなり大きくて立派なものもあるが、見たところ、たいていは19世紀後半〜20世紀初めのケルト文化復興時代以降のもののようだ。
しかし古いにしろそうでもないにしろ、円環十字架というのは絵になる姿をしているのだ。たいてい教会の敷地や修道院遺跡の緑の多い環境にあるし。
ただ見慣れない形にエキゾティシズムを感じてるだけだと言われりゃ、それまでだけどね。
ところで、アサヒグラフで見た風景に惹かれてアイルランドに行った、のではない。ガイドブックの類を見るまで、忘れてました。
でも結局、現地に行ってあちこちの墓場を巡り歩いてきたわけだけど。もちろん、良かった。それを人に伝えられるだけの写真を撮れる腕がなかったのは残念だが。
というわけでヘタクソながら、タラの丘にある教会の墓地にて
*石川文洋氏は沖縄出身の写真家で、戦場カメラマンとしての実績は、有名な沢田教一氏に劣らない。件の写真はたぶんかなり有名だと思う。石川氏の著書「戦場カメラマン」(朝日文庫)にも収録されている。「グリネードランチャーの弾を受け、バラバラになった解放戦線兵士の死体」を米兵が集めている場面とのこと。子供のように見えたのは、もともとベトナム人が小柄なうえ(若かったかも知れない)、「部分」だからだった。
アイルランドで見かけなかったものである。
自分が見かけなかっただけで、ほんとはあるのかも知れないが。
原チャリ、いわゆるスクーター、前の旅行のときも見た覚えがない。アイルランドの道交法に既定がない、とか? んなことはないだろうが。
単車はけっこう見かける。5,6人が黒っぽいライダースーツかなんか着て、大きなバイクを連ねた「中年バイク隊」を2度ほど見かけた。もっとも、これはアイルランド人かどうかわからない。大陸やイギリスからフェリーに乗ってきたツーリストかも知れないし。
ママチャリ。変速機がない、いわゆるシティ車という意味でのママチャリもほとんど見かけない。
ただ、あることはある、と思う。前回の旅行で自転車を借りようとしたとき、出されたことがあるから。
|
言葉まんまの意味の、ママが乗ってるチャリ。これはほんとに見た覚えがない。 いや、母である女性が、変速機付きのスポーツ車に乗ってたとしても見分けられないから、そういう意味じゃない。 日本では当たり前の、小さな子供乗せてるママのことだ。 アイルランドで見る自転車はたいてい変速機付きで、乗ってる人はツーリストか、学生らしき人が多い。 ただ、幼児を乗せてるお父さんは、2回くらい見たが。しかし図のとおり、フレームに乗っけてるので、なんか危なっかしい。 要するに自転車は、大人が子供を一緒に乗せて走る機能を持つツールとは見なされていない。 って、そりゃ当たり前だよ。
|
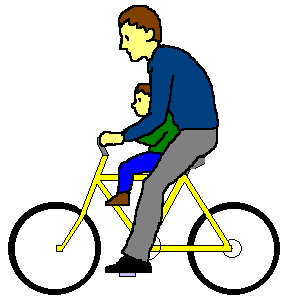 |
考えてみたら日本の自転車文化の方が特殊なんじゃないか。
海外に取材したTV番組とか見たって、ママが小さい子供を自転車の前にも後ろにも乗せて走ってるなんて、あったかな? (東南アジアのどっかならあるかもしれないが)
それも日常的な風景で、子供を乗せるための専用シートまである。
外国の人が見たら、サーカスみたい、とか、危ねー、とか思うんじゃないの? 実際、危ないし。
で、さらに考えてみたら、自転車の前にカゴなんか付いてるのも、もしかしたら日本だけ? って気がしてきた。
やっぱりTVでよく見る、中国で大量の自転車が道いっぱいに、だーっと走ってる場面。みんなカゴなんか付いてなかったような気がするなあ。
うーん、外に出てわかる自国文化の特殊性。なんちって。
聞いてみたいですね、外国の人に、ママチャリのこと。
旅行中はいつも、500ml入りのペットボトルでミネラルウォーターを持ち歩いていた。
理由の一つは、やはり自販機がないこと。もっとも町なら小さくても、コンビニというか雑貨屋の1軒くらいはある。しかし、移動の長距離バスの中で弁当食べたり、チャリであっちこっち駆けめぐるには、持ち歩いてる方が都合がいい。
もう一つ、ミネラルウォーターである理由。それは単に、ペットボトルのお茶がないから。
日本でなら、「午後の紅茶−薫るアールグレイ」とか「六条むぎ茶」とか「ジャワティー」なんか飲んでるわけで、どーも水に金出す気になれない。
でもアイルランドでは(ていうか他のたいていの国でも、だと思う)、お茶はあくまで飲むときに淹れるものだ。
それに、彼の地では水を買うことに抵抗がなくなるばかりか、何故か美味く感じるんだね。
もちろん、世界的ブランドであるevianとかvolvicとか、どこにでもある。
でも、それとは別にあるんですね、「六甲のおいしい水」や「南アルプス天然水」みたいなのが。
"Kerry Springs"ってやつは、たぶん全国的に出回ってる有名なのじゃないのかな。
"Kerry"が風光明媚の代名詞って感じの土地なので、この名前はいかにも清らかでうまそーだ。
"Tipperary"というのも、よく見かけたように記憶する。有名な教会遺跡Rock of Cashelがある、南寄りのcounty(州)で、その名前の町もある。
ゴールウェイには"Galway"というのがあった。ゴールウェイは街の真ん中にコリブ川という川が流れていて、水の街というイメージはたしかにある。でも、河口の街で、すぐゴールウェイ湾に接してるから、飲料水のイメージじゃないな。
この"Galway"だったと思うけど、飲み口に一工夫してある。
台所洗剤のボトルの先端、つまみを引っ張ると中身が出て、押しておくと出ないようになってるアレ。あれと同じ飲み口が付いてるのだ。
いちいちフタ取らなくても飲めて、でも中身はそう簡単にはこぼれない。目から鱗、ほどじゃないけど、虚を突かれましたね。あれでちゅーちゅー水吸うのは、なんとも言えん感触っす(比較対象がないもんなー)。日本にもあるのかな。自分は見た覚えがないけど。
ちなみに「桃の天然水」にあたるフルーツフレーバーの水もあった(自分は飲んでないっす)。土地柄のせいか、クランベリーとかラズベリーとか、ベリー系が多かったと思う。スーパーにはいろんな種類が揃ってた。
最近では日本でも、ベリー系出てきたみたいだけど、約2年前の時点では、この分野ではアイルランドの方がバリエーションが豊富だったみたいだ。
「食日誌」を見ていただければわかるが、今回の旅行ではカレーを何度も食べている。サンドイッチのような弁当以外の食事ではたぶん、一番頻度が高い。滞在した、Dublin、Killarney、Galway、Sligoの4つの街それぞれで、しかもGalwayとSligoでは2度ずつ食べている。まるでカレー行脚だ。
もちろん、カレーが好きだから。
ただ、好きだからって、日本にいるのと同様に海外でも美味いカレーが食べられるとは限らない(と思う)。東南アジアならともかく、他の地域では。
でもアイルランドでは食べられるのだ、美味いカレーが。
KillarneyもGalwayもSligoも、アイルランドでは地方「都市」だが、人口密度の高い日本から見れば、街としては決して大きくない。でも、いずれもちょっと歩いただけで、1カ所は本格カレーの店が見つかったし、本格じゃなくても普及版なら、メニューに載せてる店は多い。セルフサービス・カフェの軽食にさえある。サラダとしてドライカレーがあったりもする。カレーが食文化に浸透してる、と見た。
日本のカレーは、イギリスの海軍から伝わったというのが通説らしい。植民地インドから支配者だったイギリスに伝わり、イギリスの支配が長かったアイルランドにも普及した、ってことだろう。
でも何故かガイドブックとかには、あんまり書いてないみたい。日本人、カレーが好きな人多いのに。ま、美味しい店ばっかりとは限らないが。
で、誰も言わないみたいだから、ここで書いてみてるわけ。でもヨーロッパの他の国とかアメリカなんかどうなんだろう? 自分はロサンゼルスで1回、超不味いカレー食べた経験しかないけど。
ま、ロサンゼルスには3日しかいなかったから、美味いところもあったかも知れない。
でもイギリス(ロンドン)とアイルランドでは、それぞれ3日ずつでもまともなのにありついたから、やっぱり違うんだろうな。それ、'92年に最初にアイルランドに行ったときだけど、そんな短期間の間に3回もカレー食べてる(笑)。
キュー・ガーデン(イギリス)のカフェのは羊肉と鶏肉でそれぞれ味付けが違ってて美味かった。ダブリンの中華屋さんで食べたのは、何故か日本の市販のルーで作ったやつに似た味だった。どうも中華屋さんはカレー出すところがけっこうあるみたいだ。
自分の場合、カレー行脚の理由は、カレーが好きだからでもあるが、米が食べたいからでもある。
味噌汁はふだんほとんど食べないし(嫌いではない)、梅干しは嫌い。海外旅行中に、いわゆる日本食を食べたかったことはない。
しかし米は食べたい。ただ、美味しく調理された米ならなんでもいい。「ふっくら炊いた白いご飯(うるち米)」である必要は全然なく、インディカ米おおいに歓迎。
その米が大好きなカレーで食べられるんだから、渡りに船っつうか。
ちなみにアイルランドでは中華屋さんも多いので、チャーハンとかでも米が食べられる。それにデリカで、サンドイッチの中身に、ライスサラダを置いてるところもあった。要するにけっこう米が食べられるのだ。ありがたや。
海外旅行では、食事に満足できるかどうかは大きな問題だ。まず、元気で旅ができる条件だし、もし、その国の食べ物と相性が悪かったら、その国の印象そのものが悪くなりかねない。
自分が3度もアイルランドに行った理由には、きっと食べ物の相性が良いことも含まれるのだろう。
フクシアという花を知ったのは、アイルランドに出逢ったのと同じ、ある小説の中だ。
知ったと言っても名前だけで、実物を見たのは'95年、2度目にアイルランドに行ったときである。
前述の小説では、主人公がアイルランド人で、メキシコの荒野で故郷に思いを馳せる場面にフクシアが出てくる。
以下は、その一節。
ときどきぼくは自分の生まれた国、ケリーの海や山、緑の草、やさしい雨、ほこりだらけの生け垣に生えるフクシャを無性に思いこがれた。ぼくたちはフクシャを《神さまの涙》と呼んでいた。
(THE WRATH OF GOD by James Graham 邦題「サンタマリア特命隊」安達昭雄訳)
カラカラに乾いたメキシコの荒野の描写の中で、この部分は印象的だった。
で、「神さまの涙」という呼び名から、小さくて白い花を想像したのである。
さて'95年9月にアイルランドに行ったときだ。Sandycoveで、Sligoで、民家の庭で、教会の庭で、あちこちでその花を見かけた。
1m前後の低木で小さい葉がよく茂り、指先くらいの花が吊り下がるように無数に咲き乱れている。日本では見たことのないその花が「それ」じゃないかと直感した。
そのとき現地でお世話になった、語学留学中のSさんに尋ねた。Sさんは知らなかったが、調べてくれた。
「フューシァだって」
発音は違うが、間違いないだろう。やっぱりフクシアだ(*)。
でも、花は赤いのだ。
てことは「血の涙」じゃん。げげっ。
*フクシアってfuchsiaのローマ字風読みってことかな
だが、自分はフクシアがいたくいたく気に入った。ほんとはどっかから枝切って盗んで帰ろうかと思った。でもそれで栽培できるかどうかわからない。
ともあれ日本帰って調べてみた。そしたら、なんと日本でも売ってたんだね。しかも白い花とか八重咲きとか種類もいくつかあった。
で、アイルランドで見たのに近い濃いピンクのを1株買った。30cm足らずの小さいやつ、わずか300円か400円かそこら。
しかしお値段の割りには、栽培にコツがいるヤツだった。
増やすのは挿し木で簡単に増やせる。が、水はけが悪いのを嫌うのでなるべく粗い土を使わなきゃならない。肥料をやったら肥料負けして葉が赤くなっちゃう。そして高地原産のせいか高温多湿に超弱い。昨今の東京近辺の夏は、こいつには酷な環境なのだ。実際'99年の夏、10月まで続いたクソ暑さで、一生懸命4鉢に増やしたうち、3鉢が死んでしまった。
それと栽培して気付いたのは、高温多湿だと花の色が薄くなること。アイルランドで見たのと色が違ったのはそのせいで、自分が買ったのは品種としては同じヤツだったのだ。
(ちなみに、ほんとは赤じゃなく濃いピンク。口紅に「フューシァ・ピンク」という色があるそうだ)
それはさておき。
今回の旅行でのフクシア関係の収穫は、ケリーで、ディングルで、クリフデンで、ほんとに生け垣で延々と続くフクシアを見られたこと。そして「神さまの涙」の語源がわかったこと。いや、それは自分が旅行から帰った後、Mが調べてくれたんだけど(M、ほんとにありがとう!)。
ゲール語で"DEORA DE"(ジェオラジェ)。
・・・なんていい響きなんだろ。。。
アイルランドで見るあの花には、この呼び名こそが一番似合ってる(写真)。