![]() 「僕はストラッドバラのエメット・ケオーだ」
「僕はストラッドバラのエメット・ケオーだ」
旅行中に探していた本"THE WRATH OF GOD"が、アイルランドに最初に出逢った小説だったということは他の項にも書いた。
探していたのはもちろん原書だ。最初に読んだのは角川文庫版(安達昭雄訳)で、「サンタマリア特命隊」という、なにやらクサイ邦題で出ていた。
このタイトルは、当時この小説を原作とした映画が公開されて、その映画の邦題をそのまま使ったらしい。つまり映画の公開に合わせて出版されたのだろう。何しろカバーが映画の写真だったから。ロバート・ミッチャムが主人公の相棒のニセ神父を演じたようだが、流行ったという覚えは全然ない(未見)。
ところで小説には聖マルティン・ド・ポレスという聖人様(どういう聖人様か知りません)が登場なさるが、サンタマリア様は全く関与なさらない。たぶん映画では、聖マルティン・ド・ポレス様じゃ無名過ぎるので、勝手にマリア様に交替させてるんだと、だからこういうタイトルになったんだと推測している。
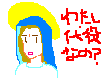
"THE WRATH OF GOD"はJames Graham名義で発表されているが、この人はJack Higginsとして有名だ。冒険、アクションものの人気作家で他にも映画化された作品がある。邦訳も数多い。以前、地元の図書館のパソコンで検索かけたことがあるが、いくつかの分館の分も含め、とんでもない数の作品がそれぞれ何冊もどーっとリストに出て焦った。それだけ貸し出しの人気もあるわけだ。
が、自分はヒギンズの作品はこの"THE WRATH OF GOD"と"A PRAYER FOR THE DYING"邦題「死にゆく者への祈り」しか読んでいない。"THE WRATH OF GOD"は人気作家ジャック・ヒギンズになる前の作品なので、かなりマイナーである。
舞台は1922年、革命後のメキシコ。アイルランドから流れてきた元IRAのテロリストの主人公が、銀行強盗してやはり流れてきたアメリカ人のニセ神父と知り合う。2人は一緒にワナにはめられ、反革命分子の掃討という危険な任務を負わされる。
ストーリーを要約すると、ものの見事に冒険、アクションもの、しかもB級だ。や、まさにその通りの作品である。しかし、よくできたエンターテインメント小説でもある。
気に入った本でも何度も読み返すことはほとんどない自分が、例外的に何度も読んで飽きない(ちなみにジャック・ロンドンの「荒野の呼び声」も例外)。
とはいえ、理由はうまく説明できない。語り口の巧さとか、けっこう考察が行き届いている印象の細部描写とかもある。が、全体にネガティブ指向なところが大きな要因だと思う。
ほぼすべての登場人物がネガティブなものを負っている。その登場人物たちの性格や行動パターンが絡み合い、然るべくして物語は悪い方向に展開していく。最後になんとかかんとか解決だけはするが、幕切れにも明るさはまるでない。
どうもそのへんが、ポジティブ、前向き、プラス思考といったものにリアリティを感じない自分の好みにはまったようだ。
ただ、あくまでも自分の好みなだけだ。リアリティがある分、冒険ものとしては荒唐無稽度が低いし、宗教的なものが濃厚に絡んでるので、万人にお奨め、という作品ではない(全然お奨めする気はない)。
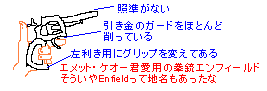
もう1点のヒギンズ作品"A PRAYER FOR THE DYING"「死にゆく者への祈り」は、ミッキー・ローク主演で映画化されてTVでも何回か放映されている。自分もTVで見たのだが、ミッキー・ロークはまったくのミスキャストで、原作の味わいは皆無に近い仕上がりだった。
"A PRAYER FOR THE DYING"でも主人公が元IRAのテロリスト、登場人物のほとんどがネガティブなものを負っている。神父が出てきて宗教的なものも絡む。"THE WRATH OF GOD"とよく似た造りなのだ。
しかし"A PRAYER FOR THE DYING"では、"THE WRATH OF GOD"に比べ主人公の過去の言及つまりアイルランドに関する描写は少なく、逆に舞台はロンドンなので地理的条件としての描写はアイルランドに近くなっている。が、それはかえってアイルランドの「匂い」は希薄にしている。
"THE WRATH OF GOD"は地理的条件がまったく異なるメキシコに舞台を置くことで、そこここに差し挟まれる短い描写から、アイルランドの「匂い」が際立ってくる効果が生まれている。また、主人公の一人称で語られることにより、読む者が主人公の主観にシンクロするほど、アイルランドの印象も強まる効果もあるようだ。
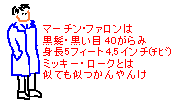
さて"THE WRATH OF GOD"の主人公左利きのエメット・ケオー君は、アイルランドはケリー郡ストラッドバラの農場で、祖父の元に、アイルランドでも最高の馬とともに育った、という設定だ。
最初のアイルランド旅行のとき地図を手に入れたので、ふとストラッドバラという地名を探すことを思いついた。
そしてケリー郡(County Kerry)内、ディングル(Dingle)半島にStradballyという地名を発見した。「ストラッドバラ」は誤植か? しかし複数の記載箇所がある。Stradballyを「ストラッドバラ」と発音するのか?
原書探しは、実はこんな「重箱な」疑問を解くためでもあった(笑)。
で、原書での表記はStradballa。たった1文字の違いだ(Stradboroughかと思っていた)。
違いの理由はわからない。しかし実際ディングルに行ってみると、小説の記述の如くフクシアの生け垣がそこら中にあったので、Stradballyである可能性は高い。もし、その周辺に競走馬の生産牧場でもあれば(昔あった、でも)有力な裏付けになるんだけどね。それはまだ未調査(笑)。
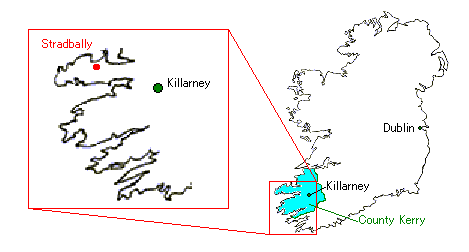
ついでのことながら、英語圏の人物名としてちょっと異色の響きがあるエメット・ケオー(Emmet Keogh)という名前についても、今ならおおよその推測がつく。
Keoghという姓はおそらくケルト語源なのだろう。アイルランドの地名には"K"で始まるものがかなりあるが、その多くがケルト語源らしい。ちゃんと調べたわけではないので全くの推測だが、姓にも"K"で始まるものが多いのではないだろうか(ケネディ大統領のKennedy家もアイルランド系だし)。
Emmetは、ケオー君の父親がFenian(対英軍事組織のメンバー)だったという設定からすると、Robert Emmetにちなんだものと思われる。Robert Emmetは1803年に武装蜂起を起こした(もちろん失敗した)人物で、反逆(イギリスの支配に対する)のヒーローらしい。
さらに最近、アイルランドで買ってきた本"Michael
Collins"で新発見。小説のケオー君が属していたとされるテロ・グループ"The Squod"に、ほんとにKeoghという人物がいたのだ(ファーストネームはEmmetではない)。
左利きかどうかは書いてなかったけどね。